国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋
285件の記事があります。
2016年11月18日鳥と私と藤前干潟
国指定藤前干潟鳥獣保護区 西部理恵
藤前干潟からこんにちは。
アクティブ・レンジャーの西部です。
突然ですが、最近、私がはまっていることは、何でしょう?
といってもわかる訳がないですよね。
それは、鳥を見ること。
鳥獣保護区のARが何を言っているんだ?!とお思いでしょうか。
当然です。私もきっと、そう思ったと思います。
けれども、私は今まで海の勉強はしてきましたが、藤前干潟に来るまでは「鳥」を見る、
という経験はほとんどありませんでした。それに加えて、自然保護官事務所のある稲永ビジターセンターの隣には、名古屋市野鳥観察館があり、鳥で分からないものがいれば、野鳥館のベテランスタッフに聞くことが多いのです。
ところが最近、ひょんなことから、事務所のフィールドスコープを引っ張り出す機会があり、
平賀ARと巡視に行く時には双眼鏡だけでなく、このフィールドスコープを持ち歩くようになりました。
当たり前ですが、フィールドスコープでのぞく世界は、双眼鏡の時よりもぐっと鳥が近い!
鳥たちのちょっとしたしぐさや、飛び立つときの顔、などが良く見えます。
藤前干潟に来てから、1年半と少しになりましたが、ここにきて改めて鳥を見る楽しさに目覚め、藤前干潟の魅力を再認識している私なのでした。
でも、写真に撮るのは難しい!
というわけで、11月16日に撮影した藤前干潟の鳥たち。
今までよりも、ちょっとだけ動きのある写真になったのではないかな?と思うのですが、いかがでしょうか。
<ハマシギ3羽 一心不乱> <ハマシギ(手前)とシロチドリ>
ちょこちょこ動くチドリ類は、撮影が難しい!
<ズグロカモメ ねらいを定めてっ!(左)・・・ あれ?すました顔?(右)>
<ぴんぼけ:ズグロカモメ(上)とユリカモメ> <ズグロカモメ 飛び立ち>
今回見られた鳥の情報
※ハマシギ(チドリ目シギ科) 準絶滅危惧種
※シロチドリ(チドリ目チドリ科) 絶滅危惧Ⅱ類(VU)
※ズグロカモメ(チドリ目カモメ科)絶滅危惧Ⅱ類(VU)
※ユリカモメ(チドリ目カモメ科)
写真にはありませんが、カモ達も沢山、飛来してきています。
雄は換羽して綺麗な羽色になってきていますよ。
干潟の鳥は遠いところにいるし・・・
鳥を見るのは良くわからない、という方は、ぜひ今週末の環境学習プログラムにご参加ください!
稲永ビジターセンターが今季開催している環境学習プログラムは、初心者の方を対象としたプログラム。
テーマは、「干潟の世界はじめの一歩」なのですが、次回は「鳥編」なのです!
この時期に沢山やってくるカモを見る講座です。
気負わず参加出来るプログラムですので、ぜひご参加くださいね。
●藤前干潟へ行こう!干潟の世界へのはじめの一歩~トリ編~
冬になると藤前干潟にはカモが沢山やって来ます。
群れで行動することが多いカモですが、その中にはカップルがいたり、
1羽だけちょっと違うカモが混じっていたり、そんなカモを探してみましょう。
日 時:平成28年11月27日(日) 10:30~12:30
場 所:稲永ビジターセンター(名古屋市港区野跡4-11-2)
定 員:20名(先着順)
参加費:おとな200円、小中学生100円、幼児無料
主催等:環境省中部地方環境事務所
藤前干潟ふれあい事業パートナーシップ事業
申込み・問合せ先:稲永ビジターセンター(TEL:052-389-5821)
★その他、藤前干潟の環境学習プログラム 今後の予定★
●石ころ干潟観察会~漂着物で工作!~
藤前干潟の石ころ干潟には、生きもの以外にも見つかるものがあります。
それが漂着物。
海岸に流れ着いた漂着物を拾ってきて工作してみよう!
日 時:平成28年12月3日(土) 13:00~15:30
場 所:藤前活動センター(名古屋市港区藤前二丁目202番地)
定 員:20名(先着順 11/19より受付開始)
参加費:おとな200円、小中学生100円、幼児無料
主催等:環境省中部地方環境事務所
藤前干潟ふれあい事業パートナーシップ事業
申込み・問合せ先:藤前活動センター(TEL:052-309-7260)
★藤前干潟のイベント情報は下記HPでチェックしてください!
2016年11月10日藤前干潟の大掃除
国指定藤前干潟鳥獣保護区 西部理恵
<そこらじゅうでヒョコヒョコ歩いているハクセキレイ>
早いもので、今年ももう11月に突入してしまいました。
藤前干潟から、アクティブ・レンジャーの西部です。
藤前干潟は伊吹山から吹き下ろしてくる風が強く、こんな内湾部でありながら波がうねる日が続いており、寒い寒い冬の到来を感じます。しかし、寒いとはいえ、楽しみもあります。事務所の前にあるグミの木には、たくさんのカワラヒワがやってきて一生懸命に実をついばむ姿が見られ、時折ジョウビタキもやってきます。
この時期にやって来る小鳥たちの姿に心が和む私たちなのでした。
<ちょっと画面が暗いですが・・・カワラヒワ>
さて、そんな冬の装いの藤前干潟では、少し前のことですが、とても沢山の人たちが集まるイベントがありました。藤前干潟の大掃除、干潟に溜まっているゴミや放置されたゴミを撤去する大掃除が行われたのです。
1つめは、
昨年度も行った国指定藤前干潟鳥獣保護区内の日光川護岸での不法投棄ゴミ撤去活動。
今年は少し時期を早めて10月25日(火)に、愛知県産業廃棄物協会名古屋支部と、愛知県、名古屋市、 中部地方環境事務所が協力して、ごみの撤去活動を行いました。
2つめは、
春と秋の恒例行事として定着してきた、藤前干潟クリーン大作戦。
今年の秋は、10月29日(土)に、庄内川の中堤や新川、藤前干潟の護岸に多数の一般市民が参加して大規模なごみ清掃活動が行われました。
まずは、1つめの日光川不法投棄ゴミ撤去活動。
少し天気が心配された10月25日(火)でしたが、100名を超える人が集まってゴミの撤去作業を行うことが出来ました。日光川の護岸は、今年も不法投棄ごみや漂着ごみがたまっている状況ではありましたが、全体としてのゴミの量は、年々、少なくなってきているようです。
今回の掃除箇所は、昨年と同じ2箇所でごみの撤去活動を行いましたが、1箇所では作業が早く済んだため、もう1箇所を集中して行うことが出来ました。
【撤去活動の様子】
最終的に回収したゴミの量は、可燃ゴミが1,710kg、不燃ゴミが1,420kgだったそうです。
その他にもタイヤなどの大きなゴミが回収されましたが、回収したゴミの量から見ても昨年度は5トンだったそうなので、減ってきたと言えると思います。
毎年行ってきたこの撤去作業によって、キレイになった干潟にはゴミが捨てにくいという状況が出来上がっていることや、ニュースなどで配信されることで、ゴミを不法投棄してはいけない、という意識が広がりつつあるのかもしれません。
参加されたみなさん、ありがとうございました。
次に、2つめの市民によるゴミの清掃活動。
今回で25回目を迎える藤前干潟クリーン大作戦は、毎年1000人を超える市民の方が集まる春と秋の恒例行事として定着してきました。
2016年の秋は、10月29日(土)に朝から大勢の人たちが藤前干潟周辺に集結してゴミ拾いを実施しました。前日には雨が降っており開催が危ぶまれましたが、当日は朝から快晴で多くの人が集まることが出来て良かったと思います。掃除の最後には、事前希望者を対象にした藤前干潟の観察会も実施されました。
【クリーン大作戦、干潟観察会の様子】
この干潟観察会は、名古屋自然保護官事務所が協力して行っています。当日は、沢山の人が清掃活動の後に残って観察会を楽しんでいかれました。長く干潟にいると少し肌寒かったかもしれませんね。
こんな風にして、藤前干潟では沢山の人たちが清掃活動に関わってくれています。
クリーン大作戦は、来年度も春、秋と開催される予定です。こちらの清掃活動には、どなたでも参加することが出来ますので、興味を持たれた方はぜひご参加ください。
こうした干潟に落ちているゴミは、自然には土に帰ることのないゴミも混ざっています。すぐにゴミがなくなる、ということはありませんが、来年の春には今年よりももっとゴミが少なくなっていると良いですね。
藤前干潟の夕日が美しい季節になってきました。
冬鳥も少しずつ増えていますので、ぜひ、藤前干潟に遊びに来てください。
<左:ダイゼン、右:ハマシギ>
★藤前干潟の環境学習プログラム 今後の予定★
●石ころ干潟観察会~カニさんを探してみよう!~
干潟と一言で言っても、いろいろなタイプの干潟があります。
今回は、石ころ干潟(礫干潟)で「カニ」をテーマに観察会を開催。
石ころ干潟にすむカニの特徴や生態を通じて、干潟の環境について学んでみよう。
日 時:平成28年11月13日(日) 10:00~12:30
場 所:藤前活動センター(名古屋市港区藤前二丁目202番地)
定 員:20名(先着順)
参加費:おとな200円、小中学生100円、幼児無料
主催等:環境省中部地方環境事務所
藤前干潟ふれあい事業パートナーシップ事業
申込み・問合せ先:藤前活動センター(TEL:052-309-7260)
●藤前干潟へ行こう!干潟の世界へのはじめの一歩~トリ編~
冬になると藤前干潟にはカモが沢山やって来ます。
群れで行動することが多いカモですが、その中にはカップルがいたり、
1羽だけちょっと違うカモが混じっていたり、そんなカモを探してみましょう。
日 時:平成28年11月27日(日) 10:30~12:30
場 所:稲永ビジターセンター(名古屋市港区野跡4-11-2)
定 員:20名(先着順)
参加費:おとな200円、小中学生100円、幼児無料
主催等:環境省中部地方環境事務所
藤前干潟ふれあい事業パートナーシップ事業
申込み・問合せ先:稲永ビジターセンター(TEL:052-389-5821)
★藤前干潟のイベント情報は下記HPでチェックしてください!
2016年10月24日環境学習プログラムで干潟を体感!
国指定藤前干潟鳥獣保護区 西部理恵
みなさん、こんにちは。
藤前干潟から、アクティブ・レンジャーの西部です。
ずいぶんと朝晩が冷え込むようになってきました。
名古屋自然保護官事務所は、建物の構造が半地下のような形状になっていることから、
名古屋でありながら特に冬は極寒の地・・・として巷では有名なのです。5月になってもフリースが必要な日があるのですが、最近では、ウォームビス推奨期間(11月から)を前倒しにして、そろそろフリース&ダウンが必要か、と冷や冷やしております。
さてさて、そんな事務所とは裏腹に、藤前干潟は絶好の干潟観察日和が続いています。
冬の渡り鳥、カモたちも続々とやって来ている今日この頃。
今年1番の行楽日和、とニュースでも言われるほど天気に恵まれた10月15日(土)、
藤前干潟では、稲永ビジターセンタースタッフによる干潟を体感する環境学習プログラムが行われました!
「干潟の世界はじめの一歩~サカナ編~」と題したこのプログラム、干潟の人気者-トビハゼ、をじっくりと知ることが出来る観察会となりました。
<水の中に潜んでいるトビハゼ>
干潟の魚トビハゼは、ずばり干潟で生きている魚です。つまり、干潟が無くなるのと共に姿を消していく運命とでも言えば良いのでしょうか。日本中で干潟が減少している今では、環境省第四次レッドリスト(汽水・淡水魚類)で「準絶滅危惧種」に指定され、地域によってはほとんど見られなくなってしまった場所もあるようです。
藤前干潟では、この時期になると小さな子どものトビハゼをたくさん見かけます。毎年毎年、藤前干潟で子どものトビハゼを見ることが出来る、干潟で実際にトビハゼを見られる、そんな機会があるというのはすごいことなんですね。

プログラム当日は、子どもから大人まで、干潟でぴょんぴょん跳びはねるトビハゼに歓声をあげていました。テレビや図鑑でしかトビハゼを見たことがない、と言う子どもたちも多く、とても楽しんでいたようです。子どもたちの中には、干潟から出たくない!と言う子もいたくらい。あぁ、そんなに楽しんでくれたんだなぁ、とほほえましくも、心の中でごめんね、と謝ったのでした。
最近は、子どもたちでも泥んこ遊びがあまり出来なくなってきているようで、干潟に入ると目の色が変わります。そうして、いろんな物を見て、いろんなことが頭の中をくるくると駆け回るのでしょう。スタッフに沢山質問をしたり、生きものの様子をじーっと観察したり、捕まえたり、とても楽しいプログラムになりました。
観察会の後は、捕まえたトビハゼやカニたちも元の干潟にリリースしてお礼を言いました。
藤前干潟は、名古屋という大都会の中にあってぽっかりと残された自然干潟です。生きものにとってだけでなく、こうして人々にとっても沢山のものを分けてくれる場所なんだ、とプログラムに立ち会うたびに思います。
皆さんも、ぜひ干潟を体感できる環境学習プログラムにご参加ください。
稲永ビジターセンター、藤前活動センターの各施設で、干潟の体感プログラムを用意していますよ。
< 藤前干潟の環境学習プログラム 今後の予定 >
●石ころ干潟観察会~カニさんを探してみよう!~
干潟と一言で言っても、いろいろなタイプの干潟があります。
今回は、石ころ干潟(礫干潟)で「カニ」をテーマに観察会を開催。
石ころ干潟にすむカニの特徴や生態を通じて、干潟の環境について学んでみよう。
日 時:平成28年11月13日(日) 10:00~12:30
場 所:藤前活動センター(名古屋市港区藤前二丁目202番地)
定 員:20名(先着順)
参加費:おとな200円、小中学生100円、幼児無料
主催等:環境省中部地方環境事務所
藤前干潟ふれあい事業パートナーシップ事業
申込み・問合せ先:藤前活動センター(TEL:052-309-7260)
●藤前干潟へ行こう!干潟の世界へのはじめの一歩~トリ編~
冬になると藤前干潟にはカモが沢山やって来ます。
群れで行動することが多いカモですが、その中にはカップルがいたり、
1羽だけちょっと違うカモが混じっていたり、そんなカモを探してみましょう。
日 時:平成28年11月27日(日) 10:30~12:30
場 所:稲永ビジターセンター(名古屋市港区野跡4-11-2)
定 員:20名(先着順)
参加費:おとな200円、小中学生100円、幼児無料
主催等:環境省中部地方環境事務所
藤前干潟ふれあい事業パートナーシップ事業
申込み・問合せ先:稲永ビジターセンター(TEL:052-389-5821)
★藤前干潟のイベント情報は下記HPでチェックしてください!
2016年10月13日藤前干潟でモニタリング調査
国指定藤前干潟鳥獣保護区 西部理恵
みなさま、藤前干潟からこんにちは。
アクティブ・レンジャーの西部です。
私たち名古屋自然保護官事務所では、毎月1回、干潟の底泥に生息する生きもの達のモニタリング調査を実施しています。研究としてやっている調査ではないので、簡略化された調査になりますが、それでも干潟に生きる生きもの達がどんな生活をしているのかを知ることが出来る楽しい調査です。
とはいえ、暑い夏には太陽を恨み、寒い冬には伊吹おろしとの闘いを繰り広げ、、、、楽しいとばかりも言っていられないのが現実です。
写真は、先月9月16日の調査のときに撮影したもので、平賀ARが集めた泥と格闘しているところです。
こうやって作業していると、地元の方達が寄ってきて物珍しげに見ていかれます。中には話しかけてくれる方もおり、生きものがいるんですよー、と言って見せたりすることもあります。
この日は、前日が十五夜のお月見という日。大潮でかなり潮が引いたため、広い干潟が拡がりました。
この時期、断然増えてくるのは、小さな小さなカワザンショウガイの仲間達。
これらをソーティング(分類し数えること)するのは、一苦労です。
そして、調査の合間に目を楽しませてくれるのは、干潟の魚・トビハゼ。
小さな子どものトビハゼ達があちらこちらでぴょんぴょん跳びはねます。
<トビハゼ:岸壁に擬態しているみたいですね!すぐ近くまでやってきました♪>
<アシハラガニ:残念ながら、ゴミが多いのです。でも、力強く生きています。>
稲永ビジターセンターには、モニタリング調査のやり方や調査結果などをパネルにして展示しています。
稲永ビジターセンターにお越しの際は、チェックしてください。
★今後の藤前干潟のイベント情報は、藤前干潟のホームページでチェック!★
2016年09月26日オオメダイチドリ?
国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 平賀歩美
皆様こんにちは。
名古屋自然保護官事務所のアクティブレンジャー平賀です。
だいぶ日差しも落ち着いて...秋ですね。
と思いカメラを持って庄内川左岸沿いを、巡視に出かけた9月14日の昼間。
ところが、この日の日中は曇り空にもかかわらず日差しはじりじりと暑く、
そして堤防の遊歩道の照り返しがまぶしくて涙がでる始末です。
右下の黒い点々が、夏にロシアやアラスカで繁殖を終え藤前干潟に渡ってきているシギ・チドリ類です。
これは干潟の一部ですが、こんな感じで多くの渡り鳥を見に出向いたわけです。
(ダイゼンとオオソリハシシギ)
私がカメラを抱える横には、人生の先輩といえるご年齢の方。
挨拶を交わしたところ、その方に「なかなか藤前干潟では見られないという貴重な鳥オオメダイチドリがいるから撮影しておくといい」といろいろレクチャーをいただきました。
オートで撮ってはいるものの「手ぶれが...」とつぶやいたら「寝ころがって撮影すべし」とのお言葉。
ということで、2人で日にさらされた熱い遊歩道に腹ばいになりながら撮影。
(3羽のメダイチドリ)
(左:メダイチドリ 右:オオメダイチドリ(?))
いかかでしょうか?
腹ばいになった効果を感じていただければ幸いです。
ちなみにオオメダイチドリとは、メダイチドリより大きく、足が長い。
メダイチドリの足は黒く、オオメダイチドリは黄色みがある。
メダイチドリは首の脇から胸にかけて濃いオレンジ色。
そして、オオメダイチドリは首まわりがぼんやりしているということです。
が、さすがに目視、ファインダー越しでは見分けることは難しいので、
パソコンで見分けるのがポイントですが、それでもなお個体差があるので見分けるのは至難の業?です。
ちなみに、野鳥観察歴の長い方に聞いたところ「メダイチドリじゃないか?」とのこと。
確かに、足の黄色みが...。胸の茶褐色が脇にかけてあるような...。
さて、藤前干潟には秋の渡りの季節がやってきており
干潮時を狙っていくと、多くの渡り鳥が見ることができます。
http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/links/index.html
(こちらのページに気象庁の潮位表が見れるページがリンクされています)
(左:ダイゼンの幼鳥 右:冬羽に変わる途中のダイゼン)
ちなみにダイゼンとムナグロ、同じチドリ目チドリ科ムナグロ属で夏羽の見た目は似ています。
が、食べる物に違いがあり好む環境が違うようです。ムナグロは昆虫類、ダイゼンはゴカイ、二枚貝等です。
また、見た目で言えば下腹部分から尾にかけて白いのがダイゼン、白黒の斑模様なのがムナグロです。
干潟にくる鳥たちについて、
稲永ビジターセンター(または藤前活動センター)にある様々な展示物と共に
藤前干潟の今を確認されると、楽しいことと思います。
http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/institution/index.html
今回、メインで鳥を取り上げましたが、底生生物も撮影しましたよ!
分かりづらいですが、写真の中にチゴガニが2匹います。探して見て下さい。
(チゴガニとフトヘナタリとカワザンショウガイ)
黄色い○の中にカニがいます!
2016年08月24日干潟の鳥と、干潟のゴミ
国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 平賀歩美
ぎらぎらと太陽が照りつける藤前干潟...
皆様こんにちは。
名古屋自然保護官事務所の平賀です。
ぎらぎらと...なんて言ってみましたが、干潟には秋の渡りの鳥が徐々に飛来し始めているのが観察できます。蝉の鳴き声や、空の雲で秋を感じることは知っていましたが、干潟の鳥で秋を感じるのは私にとって初めての体験!
(仲良く2羽で休憩中のキアシシギ)
干潟に渡ってきているシギ・チドリ類は、
夏は涼しいシベリアなどの北の地域で繁殖・子育てをして、冬はオーストラリアなどの暖かい南の地域で越冬します。その途中の中継地として干潟を利用するのですが、シベリアからオーストラリアまで約3万キロ!
それを自分の腕一本...いや、羽根一つで飛んでくるわけで、彼らの凄い能力を感じます。
(足が黄色いキアシシギ)
いったいシベリアとはどんなところなんでしょう? 彼らに聞いてみたいものです。
(岩と同化していたマガモ)
****************************
さて、鳥が賑わいを見せ始めた藤前干潟。
私たちが勤務している稲永ビジターセンターがある稲永公園も連日例のアプリで賑わっています。人で賑わうのは良いのですが、比例するようにゴミの量も増えました。こちらもゴミをゲットしてはいるのですが、
できればゴミは各自で持ち帰っていただけるようご協力をお願いしたいところ・・・。
よろしくお願いいたします!
そんなゴミ流れでもうひとつです。
藤前干潟に流れ着くゴミ、特に生物に影響を及ぼすレジンペレットとマイクロプラスチックについてです。
大雨が降って増水した後の岸際には枯れたヨシに混ざってマイクロプラスチックが塵のように散乱しています。
(左:ヨシ原に散乱するゴミの現在の様子 右:緑や赤や色鮮やかなマイクロプラスチック)
=========================
マイクロプラスチックとは...
●5mm以下のプラスチック片
●日光によってプラスチックゴミが劣化し崩壊したもの
●1mm以下になっても消えることなく水中を漂う
=========================
などなど。
干潟にあるヨシ原にゴミは多く流れ着き絡まります。
ぱっと見は大きなゴミ、ペットボトルや空き缶、その他のプラスチックゴミなどが目につくのですが、
干潟の表面に目をやると小さなプラスチック片をいっぱい確認することができます。
これらのやっかいなのは、いつか分解され自然に返ることもなく、
人力で収集しない限り永遠にここにあるか、水中を漂うことになります。
大きなゴミは拾うことは出来ても、すでに破片になったマイクロプラスチックは拾うことは困難ですね。
これらを魚類や鳥類が食べてしまうとどうなるか?
そんなことを夏の終わりに考えてみるなんていかがでしょうか。
また、稲永ビジターセンターでは、深刻さの増すマイクロプラスチック問題について、新聞記事
やインターネットの情報などについて、まとめて紹介する展示を来春まで行っています。
ご興味のある方、是非お越しください。
2016年08月19日夏の終わりの藤前干潟
国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 西部理恵
みなさま、藤前干潟からこんにちは。
アクティブ・レンジャーの西部です。
<アオサギの飛翔>
名古屋自然保護官事務所では鈴虫を育てているのですが、
ここ最近、リーンリーンと心地よい声で鳴き始めました。
外ではまだまだ蝉が鳴いていますが、
少しずつ秋の気配も感じられる今日この頃、
藤前干潟の景色も夏の終わり、秋の気配がそっと近づいていると感じます。
とはいえ、暑い暑い夏休み、皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
私たちのいる稲永ビジターセンターは稲永公園の中にあるのですが、
ここ稲永公園は某携帯アプリで遊ぶ人で連日大変賑わっており、
こんなに人が集まるんだなぁとびっくりしています。
藤前干潟を知らない人が、これをキッカケにして藤前干潟に来て、
藤前干潟について知ってくれると良いと思います。
その反面、このアプリの配信が始まってからというもの、
稲永公園内はとってもとってもとってもゴミが増えました!
ペットボトルや空き缶、そして公園の大敵「タバコの吸い殻」・・・
とても悲しい現状です。
藤前干潟に来られる皆さま、
ゴミは自分の責任で持ち帰ってください!
みんなが気持ちよく遊べるように、ぜひぜひ、お願いです!
ゴミはひょんなことから海へ流れて、
そして、やって来る渡り鳥や干潟に生息する生き物に悪影響を与えてしまいます。
捕まえたモンスターだけでなく、
実際に生息している生きものについても知って欲しいなぁと思います。
<カニを捕まえたウミネコ:藤前干潟の夏を代表する鳥>
少し話が脱線してしまいましたが、
連日のように賑わっている稲永公園を横目に、
藤前干潟の生きもの達は? というと。
秋の渡りの鳥たちが少しずつ到着しはじめており、
こちらも少しずつ賑やかになってきました。
暑くてなかなか長時間、外で観察するのは難しいですが、
賑やかになってきた干潟に、ぜひ遊びに来てください。
<せっせとエサをついばむメダイチドリ>
※よーく観察していると、ゴカイをにゅ~っと引っ張り出すところが見られます。
頑張って撮影してみたのですが、どれも遠すぎてピンぼけ。
残念ながら、皆さまにお見せできるような写真は撮れませんでした。
<ちょこちょこと動き回るキアシシギ>
※藤前干潟でみられる鳥達は、遠くの干潟にいることが多く、
立派な双眼鏡がないとよく見えないことが多いのですが、
このキアシシギは割と近くまで寄ってきてくれるので観察しやすい鳥です。
<干潟にたたずむアオアシシギ>
※この個体は黄色みの強い足をしています。
若い個体に良く見られるそうです。
近縁種のカラフトアオアシシギなどは黄色い足なので、図鑑で調べるのも一苦労。
そんなときは、お隣の名古屋市野鳥観察館へ訪ねていくとすぐに答えが返ってきます。
鳥の世界は奥が深い!
★今後の藤前干潟のイベント情報は、藤前干潟のホームページでチェック!★
2016年08月10日干潟の泥で遊ぼう!
国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 平賀歩美
皆様こんにちは。
アクティブレンジャーの平賀です。
藤前干潟ふれあい事業の「干潟の泥で遊ぼう」が8月3日(水)に行われました。
当日に雨が降ったりしないか、きちんと潮が引いて干潟は出るだろうかと
どきどきしながらついに迎えた8月3日・・・。
やったー! 無事に晴れました!!! 良かった!!!
実は前日に警報が発令されるレベルの大雨が降り、
帰宅途中に電車は止まるし、というなかなかの悪天候だったのです。
そのような状況だったので、たとえ晴れても雨による増水なども心配をしていましたが、
そんな心配はよそに無事にゆっくりと干潟は現れて、参加者30名全員で干潟に入ることができました。
みんなでみお筋を渡り・・・
干潟に上陸した後は、班に分かれて干潟と干潟に棲む生き物を
じっくりと観察・体験する干潟ビンゴをしました。
今回は参加対象者が小学校1年から3年ということもあって、
とにかく「泥で遊びたい!」という子供達・・・。
と思いきや、一緒に入ってもらっている保護者の方達も干潟の泥に触れたことを
とても楽しんでいらっしゃった様子でした。
藤前干潟は昔、牡蛎の養殖をしていたこともあり、
現在も干潟入り口のみお筋には蛎殻があちこちに確認できます。
これを踏むと怪我をする恐れもあるので、通り道の部分の牡蛎を網でさらってから
基本的に靴下やマリンソックスなどを履いて干潟に入ってもらいます。
これにより、直接足の裏で砂の感触を感じることは少ないのですが、
足がゆっくりと埋まる感触は干潟ならではです(足を取られるので注意も必要です!)。
頭の上には広い空、遠くまで見える干潟越しに浮かぶ名港トリトン、
たまにウミネコが近くまでやってきたりもして、
名古屋という大都市の中での解放感を感じながらゲームをしたり、
泥を掘ったり、生き物を見つけたりして皆で楽しみました。
***************************
さて、この前日にも干潟に入り、雨の日プログラム用に散々「ヤマトシジミ」を探しに、
干潟から出てくる生き物はソトオリガイやゴカイなどで、
目的のヤマトシジミは殆ど取ることができなかったのです(生き物は後でリリースします)。
しかし、今回は干潟の上でも場所が少し新川の寄りだったため、
なんとヤマトシジミがざくざくと出てきました。
同じ干潟の上でも環境は様々で、少し場所がずれるだけでも生息する生物が違うようです。
干潟と一言でいっても、季節によって、また場所や環境によって全然生息している生物は違うので、
生き物大好きな子供達には、是非、いろんなイベントに参加して
その都度新しい発見をしてほしいと思います。
さて、参加者の殆どの方が干潟に入ることが初めてだったこの日、
楽しかった干潟での泥遊びがあっという間に過ぎ
「時間が短い!」という声を聴き後ろ髪を引かれながらも
約1時間の干潟体験は無事終了しました。
とにかく晴れて良かった!イベントデーでした。
2016年07月19日レンジャー・アクティブレンジャー写真展 @愛知県緑化センター
国指定藤前干潟鳥獣保護区 平賀歩美
今回は7月から新たな場所で始まった
レンジャー・アクティブレンジャー写真展のお知らせです。
******************************
現在7月16日(土)から8月4日(木)まで豊田市にある愛知県緑化センターで、
レンジャー写真展を開催しています。
施設・交通案内は愛知県緑化センターHP(下記アドレス)で確認出来ます。
=========================
http://www.aichi-park.or.jp/ryokka/
=========================
名古屋自然保護官事務所では本年度2回の写真展を開催します。
先月開催を終了した、碧南市にある碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学館での写真展は
お子様連れで賑わいを見せてましたが、今月は静かな豊田市の山中にある施設での開催となります。
緑化センターでは四季の花を楽しめる他、センター内の昭和の森は全国森林浴100選の森に
選ばれている場所だとそうで、森林浴で健康効果を楽しむと共に
レンジャー・アクティブレンジャー写真展をお楽しみください。
******************************
さて、裏方は見せない方が...と思いつつも設営の風景を少々。
緑化センター本館2階の左手にあるのが今回の会場です。
5面の壁にはまだ何もなく...脚立、釘などを使ってこつこつと写真を飾っていきます。
だいぶ形になりまとまってきましたが、完成まではあと一歩です。
クロスがかかっている机の上には施設の方がつくられた木製のカニや鷺草(サギソウ)の鉢植えが
偶然にもありましたので「干潟つながりでコラボ!」と一緒に展示してみたりと、
施設のレイアウトを思案しながら会場設営の作業を進めます。
と、過ぎること約2時間。おまたせいたしました。
ついに会場の完成です!
さて、愛知県緑化センターでの展示風景はこんな感じですが、
緑化センターだけあって休憩スペースにもふんだんに木が使われています。
多くの方が丸太のベンチで休みながらも写真を眺めてくださることを願ってます。
足をお運びいただいた際にはぜひともアンケートの記入!?をよろしくお願いいたします。
前回協力いただいた碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学館、
今回展示会場を貸して下さる愛知県緑化センター等、
いろいろな方のお力添えがあり開催される写真展であることを実感した次第です。
******************************
最後に、愛知県緑化センター終了後には9月から白山で、その後伊勢志摩で写真展が開催されます。
お楽しみに!












































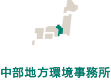
伊吹おろしが吹き始めた藤前干潟からこんにちは。
名古屋自然保護官事務所のアクティブレンジャー平賀です。
(オスのヒドリガモ)
国土の3分の2が森林の日本。中部地区国立公園のアクティブレンジャー日記を見ていると、
美しく紅葉している山の写真に胸が躍ります。
そんな雄大な山の紅葉にスケール感では負けますが、
名古屋自然保護官事務所がある稲永公園の落葉樹も紅葉しています。
また、この季節に色が変わるのは木だけではありません。
藤前干潟に渡ってくるカモたちも、オスは地味なエクリプスから美しい繁殖羽に変わっていきます。
※エクリプス...オスのカモに見られ夏から秋に見られる非生殖羽。メスのような地味な羽に換羽する
さて、そのような中、11月27日(日)に稲永ビジターセンターでは、
環境学習プログラムの「干潟の世界へのはじめの一歩【トリ編】」が行われました。
この環境学習プログラムは、藤前干潟の観察会に初めて参加する人を対象としたプログラムとなっており、
今回はその第三弾となります。
朝からあいにくの雨模様ではありましたが、
まずは室内で、カモ類を探すカードゲームやオナガガモの渡りの紙芝居、
スタッフ手作りの実寸大のぬいぐるみ!等でカモの生態を学習した後、
(左:名古屋市野鳥観察館からバードウォッチング 右:稲永公園から野鳥を観察)
お隣の名古屋市野鳥観察館へ行き、スタッフからの解説を聞きながらスコープで
干潟にいるカモ始めミサゴやダイシャクシギなどを観察しました。
それから小雨であったこともあり少しだけ屋外に出て、
鳥の鳴き声を聞くなど五感を使って間近でカモやカモメ類を観察しました。
(藤前干潟に飛来してくるカモについて振り返り)
最後は、また室内に戻ってみんなで振り返りです。参加された方も冬の藤前干潟や渡り鳥について、
新しい発見があったのではないでしょうか。
ちなみに環境省が行っている渡り鳥の飛来状況調査によると、
藤前干潟で12月上旬に見られた種としてカモ類だけで11種、数としては約4000羽!
1日数時間のカウント調査でこの数になります。
(こちらに泳いで来るスズカモ御一行様:目が黄色で体が黒と白いオスと体全体が黒いメス)
(11/24のカモ達。庄内川のヨシ原の脇で休むカモの群れ)
満潮でも干潮でも藤前干潟のあちこちで、
美しい繁殖羽に変わったカモ達の食事風景や寝姿、泳ぐ姿等々が見られます。
また、雨でも鳥は観察できると思いますのでご心配なく。
(左:ヒドリガモのメス 右:カンムリカイツブリ(カモではありません...))
さて、2016年もあと30日ほど。2017年(来年は酉(トリ)年です!)が見えてきましたね。
ということで、来年予定されている藤前干潟でのイベントのご紹介です。
○藤前干潟ふれあい事業 藤前干潟サイエンスカフェ○
【藤前干潟とつながる海-伊勢湾の流れ-】
藤前干潟にすむたくさんの生きものたちを支える環境をつくっている海の流れ。藤前干潟とつながる海-伊勢湾-や藤前干潟のまわりにはどんな流れがあるのかを学ぼう!
【お問合せ・お申込み先】
日 時:1月28日(土) 13:30-15:00
場 所:稲永ビジターセンター 1階 レクチャールーム(名古屋市港区野跡4-11-2)
内 容:藤前干潟にすむ沢山の生きものたちを支える環境をつくっている海の流れ。藤前干潟とつながる海-伊勢湾-や藤前干潟のまわりにはどんな流れがあるのかを学ぼう!
行き方:あおなみ線「野跡」駅下車 徒歩15分
定 員:20名
申込み:事前申込み 締切り1月23日(月)必着
参加費:無料
問合せ:環境省名古屋自然保護官事務所(TEL:052-389-2877)
飲み物やお菓子の持ち込み大歓迎!
http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/event/index.html
是非チェックしてみて下さい。
今回の干潟観察会の主役はカモでしたが、
今、藤前干潟ではカモメ類、チドリ類・シギ類と
多くの種類の鳥を観察出来ます(12/2にはハマシギが1128羽カウントされました)。
(11/16撮影。ユリカモメ、ハマシギ、コガモなど)
どんな鳥が見られるのかは...鳥の気分次第?!ではありますが、
伊吹おろしに負けないよう、防寒対策をしっかりしてお越し下さい。
藤前干潟でお待ちしています。