中部山岳国立公園 松本
241件の記事があります。
2006年11月16日上高地閉山祭
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
2006年11月14日白く輝く乗鞍岳
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
このところの天気の変化はめまぐるしく、松本では12日に初雪を観測しました。周辺の山々の積雪は寒波が訪れるごとに次第にその量を増しているようです。
インターネット自然研究所の「乗鞍高原からの乗鞍岳」のライブカメラを見ると、剣ヶ峰の白くなっていく様子や、カラマツの落葉等の変化がよくわかります。
↓11月3日の画像

↓11月8日の画像

↓11月13日の画像

※10日11時にカメラの保守点検を行ったため、それ以降の撮影範囲が若干変わりました。
ライブカメラの参照先はインターネット自然研究所です。全国の国立公園のライブ映像が見られます。静止画で撮影している所と動画から変換している場所があります
※「乗鞍高原からの乗鞍岳」はデジカメによる静止画撮影なので、かなり綺麗な画像だと思います。しかも過去5年分の蓄積があります。
今日の乗鞍岳は厚い雲に覆われています。北アルプスは完全に冬山となりました。入山できるのは、十分な装備を持って必要な経験を積んだ人達に限られます。我々アクティブレンジャーの仕事も事務所内での作業が中心となります。
インターネット自然研究所の「乗鞍高原からの乗鞍岳」のライブカメラを見ると、剣ヶ峰の白くなっていく様子や、カラマツの落葉等の変化がよくわかります。
↓11月3日の画像

↓11月8日の画像

↓11月13日の画像

※10日11時にカメラの保守点検を行ったため、それ以降の撮影範囲が若干変わりました。
ライブカメラの参照先はインターネット自然研究所です。全国の国立公園のライブ映像が見られます。静止画で撮影している所と動画から変換している場所があります
※「乗鞍高原からの乗鞍岳」はデジカメによる静止画撮影なので、かなり綺麗な画像だと思います。しかも過去5年分の蓄積があります。
今日の乗鞍岳は厚い雲に覆われています。北アルプスは完全に冬山となりました。入山できるのは、十分な装備を持って必要な経験を積んだ人達に限られます。我々アクティブレンジャーの仕事も事務所内での作業が中心となります。
2006年11月01日乗鞍エコーライン冬季閉鎖
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
県道乗鞍岳線(乗鞍エコーライン)の三本滝から上は、11/1から冬季通行止め期間に入ります。例年ですと10月中に降雪があった時点で通行止めとなることが多いのですが、今年はどうにか最終日まで持ちました。
この三本滝のゲートそばに駐車場があり、県特別名勝「三本滝」の見学場所でもあります。※滝までは遊歩道を片道1km(徒歩30分程度)を歩く必要があります。
でも実は、三本滝が見事な景観を見せるのは6月から夏にかけての雪解けの時期です。冬場は遊歩道も雪に閉ざされます。
↓三本滝のゲート付近(10/31撮影)

↓三本滝の真ん中の滝(左は6/6PM撮影、右は10/31AM撮影)

※7月の大雨で滝の前の景観が若干変わったように見えます
おまけ
↓まいめの池からの乗鞍岳(10/31撮影)

広葉樹はほとんど落葉しましたが、まだまだカラマツ(落葉松)の黄葉が綺麗な所があります
↓鈴蘭橋からの乗鞍岳(10/31撮影)

この三本滝のゲートそばに駐車場があり、県特別名勝「三本滝」の見学場所でもあります。※滝までは遊歩道を片道1km(徒歩30分程度)を歩く必要があります。
でも実は、三本滝が見事な景観を見せるのは6月から夏にかけての雪解けの時期です。冬場は遊歩道も雪に閉ざされます。
↓三本滝のゲート付近(10/31撮影)

↓三本滝の真ん中の滝(左は6/6PM撮影、右は10/31AM撮影)

※7月の大雨で滝の前の景観が若干変わったように見えます
おまけ
↓まいめの池からの乗鞍岳(10/31撮影)

広葉樹はほとんど落葉しましたが、まだまだカラマツ(落葉松)の黄葉が綺麗な所があります
↓鈴蘭橋からの乗鞍岳(10/31撮影)

2006年10月26日紅葉の終わりに近づく乗鞍高原
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
天気が回復した25日に乗鞍高原に行きました。紅葉の状況は、一の瀬園地(標高1400?1500m)ではシラカバはほぼ落葉しており、カエデは少し紅い葉が残っている程度、ミズナラの葉が見頃でした。全体的には「色あせ始め」なのでしょう。現在「紅葉見頃」なのは、番所(標高1300m付近)のモミジです。庭先や道路際に人工的に植えたもの(ここは公園外)が綺麗でした。乗鞍高原の紅葉は位ヶ原で9月下旬に始まったので、およそ1ヶ月もの長い間どこかで見頃が楽しめるのですね。
↓一の瀬野営場から見た紅葉(10/25撮影)

↓一の瀬園地のカエデの紅葉(10/25撮影)

↓番所の道路際にあったモミジの紅葉(10/25撮影)

乗鞍高原は紅葉の終わりが近づき、スキーシーズンまでの短い期間ですが利用者の少ない静かな季節を迎えようとしています。
↓一の瀬野営場から見た紅葉(10/25撮影)

↓一の瀬園地のカエデの紅葉(10/25撮影)

↓番所の道路際にあったモミジの紅葉(10/25撮影)

乗鞍高原は紅葉の終わりが近づき、スキーシーズンまでの短い期間ですが利用者の少ない静かな季節を迎えようとしています。
2006年10月24日紅葉情報?松本自然環境事務所
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
2006年10月15日乗鞍高原自然観察会?秋の紅葉ウオッチング
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
2006年10月12日乗鞍高原の上と下
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
2006年10月11日初冠雪?乗鞍岳
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
この三連休は例年にない強い寒波が北アルプスを襲いました。7日は家で休息していましたが、8日は上高地の交通量調査で平湯のシャトルバス乗り換え場にいました。この日は乗鞍岳スカイライン・エコーラインともに山頂付近の積雪のため朝から通行止めでした。せっかく乗鞍岳の紅葉を楽しみに来て頂いた方々には大変残念でしたが、大部分の方々が上高地に向かわれたようです。平湯は一日冷たい雨で、冬の作業服が必要な寒さに震えながらの仕事でした(泣)。10月に雪の降ることがあると頭では分かっていても、なかなか服装や持ち物にまで気が回りません。
9日はようやく天気が回復し、乗鞍岳の初冠雪が見られました。
↓乗鞍高原の牛留池から乗鞍岳を望む

9日も通行止めでしたが、バスもタクシーも通らない静かな道をプライベートでのんびり歩きました。
↓乗鞍エコーラインから山頂方面を望む

位ヶ原付近の紅葉は終わりに近づき、見頃は三本滝付近に下がってきています。
乗鞍エコーラインの通行止めは10日午後に解除されましたが、これからの季節は雪になることが多くなりますのでお気を付け下さい。
9日はようやく天気が回復し、乗鞍岳の初冠雪が見られました。
↓乗鞍高原の牛留池から乗鞍岳を望む

9日も通行止めでしたが、バスもタクシーも通らない静かな道をプライベートでのんびり歩きました。
↓乗鞍エコーラインから山頂方面を望む

位ヶ原付近の紅葉は終わりに近づき、見頃は三本滝付近に下がってきています。
乗鞍エコーラインの通行止めは10日午後に解除されましたが、これからの季節は雪になることが多くなりますのでお気を付け下さい。
2006年10月06日自然解説指導者研修?清里の秋
中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 山崎 光一
先月の半田ARの日記にあった「自然解説指導者研修」の基本研修のうち、秋の実践コースが10月2日?5日に山梨県北杜市の清里高原で行われました。全国の公園関係者やパークボランティアの方、そして我々アクティブレンジャーも私を含めて6名が参加しました。自然解説と言うよりも、自然体験を通じて環境学習を行うという趣旨です。講義を受けながら、清里の秋をテーマに新しい自然体験プログラムを4人グループで完成させます。最初こそ意見の食い違いがありますが、同じ目的をもつ仲間として、人前で発表できるレベルにまで練ることができました。
研修が始まる前に、「八ヶ岳自然ふれあいセンター」を見学しました
↓星野道夫展「星のような物語」を見ることができました

プログラム作りの前に、講師によるお手本が行われました
↓好きな葉っぱ3枚を集めました

みんなが集めた葉っぱを並べると

↑意外と綺麗なものですねー
我が班で考えたプログラムは「キノコ美人を狙い撃ち」です
一言で説明すると「キノコのべっぴんさん探し」なのですが(笑)

黒布の上において、なぜこのキノコを選んだが説明してもらいます
「色白でほんのりピンクのほっぺ」だそうです(なるほどと思いました)
秋の自然観察会に応用したいですね
研修が始まる前に、「八ヶ岳自然ふれあいセンター」を見学しました
↓星野道夫展「星のような物語」を見ることができました

プログラム作りの前に、講師によるお手本が行われました
↓好きな葉っぱ3枚を集めました

みんなが集めた葉っぱを並べると

↑意外と綺麗なものですねー
我が班で考えたプログラムは「キノコ美人を狙い撃ち」です
一言で説明すると「キノコのべっぴんさん探し」なのですが(笑)

黒布の上において、なぜこのキノコを選んだが説明してもらいます
「色白でほんのりピンクのほっぺ」だそうです(なるほどと思いました)
秋の自然観察会に応用したいですね













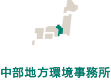
↓まいめの池と乗鞍岳山頂方面の雪雲(11月29日撮影)
※池の奥の小高い場所から池全体を撮影しました