2012年6月18日
2件の記事があります。
2012年06月18日登山者カウンター設置
上信越高原国立公園 志賀高原 アクティブレンジャー則武 敏史
「登山者カウンター」という機器があります。歩道(登山道)の脇に設置し、機器の前を通る人数を自動でカウントするものです。山歩きをされる方はどこかで見たことがあるかもしれません。
長野自然環境事務所では各地区のアクティブ・レンジャーが主体となって設置、点検・データ回収、撤去、データ整理を行っています(今年度は管内の20地点に設置の予定です)。

今回、登山者カウンターを苗場山の祓川登山口(新潟県南魚沼郡湯沢町)に設置しました。標高は約1,370mですが、5月下旬まで営業するスキー場の敷地内なので、まだ雪が残っています。
ここに設置した理由は、祓川ルートは新潟県側からの苗場山登山に最も利用されるルートで、環境省が歩道を整備しており、これによって利用者数に変化があるかを知るためです。

登山者カウンターがあると気になるかもしれませんが、登山者カウンターの前で立ち止まると誤カウントの原因となるので、気にせずに歩いてください。また、登山者カウンターに触れないでください。ご協力をお願いいたします。
さて、登山道の情報です。スキー場の方によると、祓川登山口から苗場山頂への道はまだ半分以上が雪道とのことなので、それなりの装備が必要です。また、雪の残る樹林帯ではルートが分かりにくくなるのでご注意ください。
長野自然環境事務所では各地区のアクティブ・レンジャーが主体となって設置、点検・データ回収、撤去、データ整理を行っています(今年度は管内の20地点に設置の予定です)。

今回、登山者カウンターを苗場山の祓川登山口(新潟県南魚沼郡湯沢町)に設置しました。標高は約1,370mですが、5月下旬まで営業するスキー場の敷地内なので、まだ雪が残っています。
ここに設置した理由は、祓川ルートは新潟県側からの苗場山登山に最も利用されるルートで、環境省が歩道を整備しており、これによって利用者数に変化があるかを知るためです。

登山者カウンターがあると気になるかもしれませんが、登山者カウンターの前で立ち止まると誤カウントの原因となるので、気にせずに歩いてください。また、登山者カウンターに触れないでください。ご協力をお願いいたします。
さて、登山道の情報です。スキー場の方によると、祓川登山口から苗場山頂への道はまだ半分以上が雪道とのことなので、それなりの装備が必要です。また、雪の残る樹林帯ではルートが分かりにくくなるのでご注意ください。

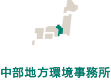
今年、僕がいる白山自然保護官事務所では、北陸地方の主だった川の水源であり、私たちの暮らしと生きものの命を育む白山の水に焦点を当て、白山国立公園内の水にかかわりのある場所を巡る観察会を5回開催します。
その第二回「白山 水を巡る旅~根倉谷園地で自然体験~」を今週末開催しますので、お知らせします。
日 時:平成24年6月23日(土) 8:30受付開始 ※雨天延期
問合せ:白山自然保護官事務所 076-259-2902
web↓↓
http://c-chubu.env.go.jp/pre_2012/0614a.html
22日10時まで募集中です。皆様のご参加をお待ちしております!
また、前回の日記で下見の報告をしましたが、自然観察会「白山 水を巡る旅~初夏の赤兎山・赤池湿原巡り~」を6月10日に行いました。
当日は、天候が悪い中、14名お集まりいただきました。
古くから使われている越前禅定道を歩き、霧の中で沢山の鳥類や高山植物に会えました。
既に山は夏の気配・・耳を澄ますとヤブサメやオオルリ、ホトトギスなどの夏鳥の声が聞こえました。
登山道はまだ残雪が残っていて、リュウキンカ等、雪解け後に咲く花が見られました。
地面が雪どけ後の春先の植物が咲いていましたが、空を飛んでいる鳥は夏の時期のもので・・近い場所でも環境の違いが現れていて面白いと思いました。
また、小原峠から赤兎山の間の登山道の稜線が、ちょうど手取川と九頭竜川の集水域の境界線になる(源流域にあたる)のを現地に立って体感してもらいました。
立山で言う大河川と言えば常願寺川ですね。
白山は、福井は九頭竜川、石川は手取川、岐阜は長良川、富山は庄川の
4県に大河川が流れ、水の恵みを与えています。
また、水繋がりで、何故、赤池湿原が重要視されているのか・・考えてもらいました。
【赤池にて解説・・トンボいなかったですねー】
ラムサール条約湿地って知っていますか?
石川県内だと片野鴨池がその湿地になります。
世界を股にかけた鳥類が、長い距離を移動する中継地点として重要な役割を果たしています。
スケールは小さいですが、池や水たまり等がある程度の間隔にあると、鳥類と違って、長距離の移動に労力がかかるであろう、トンボの様な昆虫の中継地点になります。
そして、この赤池が高層湿原と呼ばれ、高所で湿地を利用する昆虫たちの楽園になっているのです。
そして、カオジロトンボがこの赤池を分布の西限になっていて、彼らにとっても、学術的にも、とても重要な湿地になっています。
こんな話を聞きながら、赤池をもう一度見てみると、イメージが変わってくるかもしれないですね。
こんな小さな水たまりも、そんな大きな役割を果たしているんです。
白山国立公園50周年のフラッグ(標語)として以下が掲げられています。
「白山は 水と命の源 未来に引き継ぐ 私たちの宝」
生きものにとって水は必要不可欠です。
【サンショウウオも水が必要です】
「白山 水を巡る旅」よろしくお願いします。