
アクティブ・レンジャー日記 [中部地区]
【シンポジウム】未来につなぐ北アルプス。登山道について学び考える2日目
2025年02月10日
立山
立山管理官事務所の一ノ枝です。
令和7年2月15,16日に「北アルプストレイルプログラムあり方検討会 シンポジウム(in富山) 持続可能な登山道維持について考える」を開催します。
今回は前回に続き2日目の内容に関して注目の登壇者やテーマ内容をピックアップしています!
山を愛し、その地を守るために情熱を注ぐ方々が、貴重な知見を共有してくださいます。
2日目は大学の先生や研究者をお招きしてご登壇いただきます。
登山道管理をする上での効果的な調査や計画、人材育成、組織の立ち上げなど貴重なお話をいただきます!
本シンポジウムは事前申込み制(入場無料)となっております。
詳細・お申込みは以下リンクから↓
https://nationalpark-japanesealpstrail.jp/toyama-news/447/
では2日目の登壇者の方をご紹介します。
八巻 一成 氏(国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所) 2日目登壇
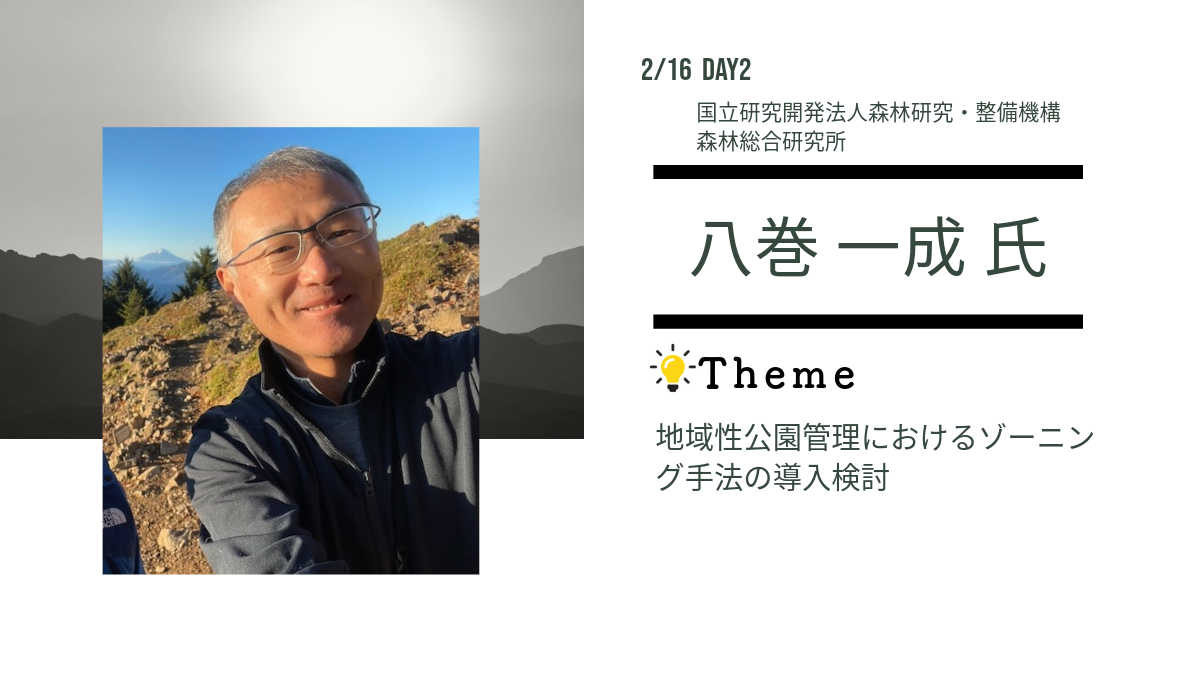
テーマ:山岳公園管理におけるゾーニング手法の導入検討
国立公園の管理運営において保護と利用のバランスを検討する際に重要視される「ゾーニング」手法。その導入と効果を、大雪山国立公園での事例を交えながら解説!利用者ニーズと自然保護をどう両立させるか、実践的な知識をお話しいただきます。

< 注目ポイント >
• ゾーニングの意義とその活用方法
利用と保全のバランスを取るために検討される「ゾーニング」とは?現場の課題や導入の際の留意点などを提言します。
• 地域協働による管理運営の重要性
日本の国立公園は行政や民間企業、団体などの様々な組織が協働で運営しています。
今後地域にとって大事な計画を作る際に大事な考えである「ガバナンス」と「マネジメント」という2つの視点で自然公園管理を考察。意思決定から運営までの流れを学びます。
•山岳公園におけるゾーニング手法の導入と成果
利用者が求める自然体験の種類やレベルと原生自然を保護するべきレベルのバランスが取れないと過剰な開発行為や適切な自然保護を実現することができません。北海道の大雪山での具体的導入事例とその効果を知ることで北アルプスにおける登山道の利用と保護に関する未来を考えていきます。
続いてご登壇いただくのがこの方です!
渡辺 悌二 氏(北海道大学) 2日目登壇
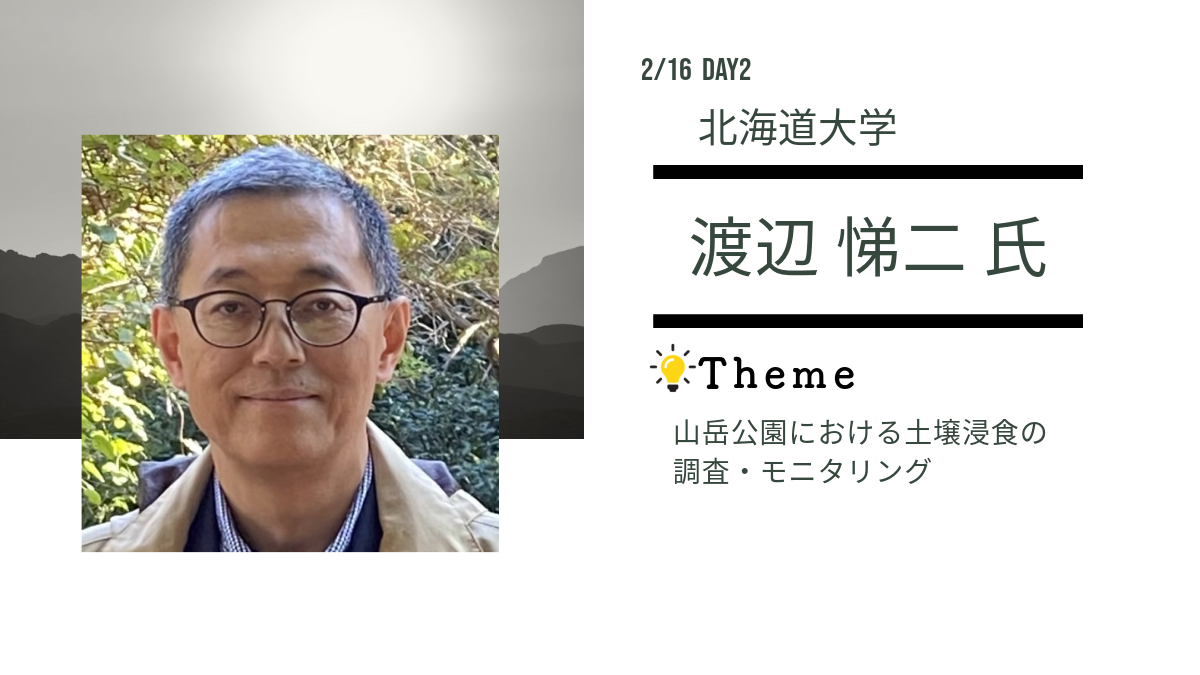
テーマ:山岳公園における土壌浸食の調査・モニタリング
登山道の土壌浸食を中心とした荒廃状況の調査を通じて、自然環境保全に必要な情報の整理や活用について考えます。他地域での調査事例や研究成果を交えながら、調査から得られる知見とその活用法を探ります。

< 注目ポイント >
• 現状把握の重要性
自然環境の現況を正確に把握することで、具体的対策に必要な情報が整います。これまでの調査活動を経てどのような情報が有効かを解説いただきます。
• 広大かつ長距離の登山道周辺における効率的な調査
広大な山岳地において長距離の登山道を調査するための方法や、公園管理者・学術調査チーム・NPOの協働による効率的な調査方法について考えます。
• 調査結果の公表と活用法
調査で得た情報を分かりやすく整理・発信し、現地で活用するための意見交換や意思決定の枠組みの在り方について学びます。
次にこの方にご登壇いただきます。
下嶋 聖氏(東京農業大学) 2日目登壇

テーマ:地理情報システムとリモートセンサリング技術を活用した景観、自然環境解析
高度な地理情報システム(GIS)やリモートセンシング技術を駆使した自然環境解析の意義と効果について解説。現場で得られるデータの可視化から、計画への反映まで、その活用法をお話しいただきます。

< 注目ポイント >
• 自然環境解析におけるGIS活用の意義
GISを活用してデータを可視化することで、現地の状況を的確に把握。継続的なモニタリングで得られる成果と変化を追う調査計画について考察します。
• 管理計画への具体的な反映
科学技術を活用した管理計画策定の実例を紹介。現地での整備にどのように活用できるのか、単発な調査、整備活動ではなく、継続的な保全活動につなげる視点を学びます。
お昼休憩の後、残りお2人の方にご登壇いただきます。
岡崎 哲三氏(一般社団法人大雪山山守隊)2日目登壇

テーマ:大雪山国立公園における登山道保全管理の実態と課題
日本最大規模の山岳公園である「大雪山国立公園」で現場の保全管理を担う岡崎氏が、近自然工法を行う意義や課題、長距離の登山道を持続的に維持するためについてのヒントをお話しいただきます。

< 注目ポイント >
• 近自然工法を用いた登山道保全
自然との調和を目指した近自然工法の意義を解説。持続可能な管理のために、現場で取り組むべきことを具体的に提言します。
• 人材育成の課題と展望
全国で保全講習を行う中で感じた、人材育成の難しさや課題点を共有。今後の学びのプログラム設計に役立つポイントを紹介します。
• 登山道管理を職業として確立するために
山岳登山道の管理を「生業」にするために必要な枠組みや仕組みについて、現場の視点から提案します。
最後にご登壇いただくのがこの方です。
勝俣 隆氏(一般社団法人トレイルブレイズハイキング研究所) 2日目登壇

テーマ:米国における登山道管理体制の事例について
アメリカでのトレイル管理体制と、日本の登山道管理との比較を通じて、北アルプスの登山道管理に関する課題と解決策を考えます。持続可能な管理をするため組織やチーム作りについてもお話いただきます。

< 注目ポイント >
• 米国のトレイル管理体制の実態
ロングトレイルを管理する団体について背景や取組事例を紹介。地域団体と行政が連携して行う管理手法を学びます。
• ボランティア参加型の整備事例
ボランティア(ハイカー)が積極的に参加する登山道整備の仕組みを解説。現地における受入れ組織の役割や将来的なトレイルの計画作成への関与について学びます。
• 北アルプスへの適用可能性
日本、特に北アルプス富山側における登山道管理の課題意識を共有し、アメリカの事例を踏まえた解決策のヒントを得ます。
未来につながる北アルプスへ!有識者を含めたパネルディスカッション

2日目の後半パートはご登壇いただいた方々や有識者を含めたパネルディスカッションを行います!こちらはオンライン配信はなく会場のみとなりますので是非会場まで足を運んでいただけると幸いです。
2日目は中部山岳国立公園の登山道の未来を見据えて今後の計画作りについて語っていただきます。そのために今後進めていく上で重要な検討事項について議論を深めていただきます。
ワクワクするビジョンを描きつつ、現実の計画や行動に落とし込んでいくにはどうすればよいのか。
きっと他のエリアで取り組まれる際にも参考になることがたくさんあると思います!
【登壇者(パネルディスカッション)】
野川 裕史氏(環境省中部山岳国立公園管理事務所長)
中森 健太氏(環境省立山管理官)
富山県自然保護課(登壇者未確定)
渡辺 悌二氏(北海道大学)
八巻 一成氏(国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所)
下嶋 聖氏(東京農業大学)
勝俣 隆氏(一般社団法人 トレイルブレイズハイキング研究所)
岡崎 哲三 氏(一般社団法人 大雪山山守隊)
伊藤 二朗氏(雲ノ平山荘・雲ノ平トレイルクラブ)
石川 吉典氏(薬師岳奥黒部山域 三俣山荘)
大宮 徹氏(NPO法人 富山県自然保護協会)

シンポジウムを通じて、北アルプスの「いま」を知り、「未来」を考えるきっかけを作りませんか?
本シンポジウムは事前申込み制です。(入場無料)
お申込み、詳細は下記ページにてご確認ください。
https://nationalpark-japanesealpstrail.jp/toyama-news/447/
皆さまのご来場を心よりお待ちしております!