
アクティブ・レンジャー日記 [中部地区]
海の「くっつき虫」はどこがお好み?
2013年02月26日
名古屋
藤前干潟周辺では、岩石表面や堤防岸壁にフジツボや
カキの仲間がたくさんくっついている様子を観察する
ことができます。これらは「付着生物」と呼ばれており、
海水の影響がある水域で何かにくっついて生活する生き物です。
稲永ビジターセンター1Fのレクチャー室前には、
「フジツボコーナー」があり、フジツボの面白い生態を
紹介しています。フジツボを含めた付着生物がどんな物に
くっついて成長していくのか、分かりやすく展示できないかと考え、
色や材質の異なった板を河口域に設置して、生物が付着する様子を
観察してみました。
~方法~
実験に用いた板は4色(白・黒・赤・黄)の塩ビ板とアルミ板です。
また、実験板は表面状態の違いで、付着生物の付きやすさに差が見ら
れるのか調べるため、無加工の光沢板と表面に粗面加工を施した板の
2種類の実験板を作成しました。
実験は昨年5~12月の期間で実施し、実験板ユニットは稲永ビジター
センター前の庄内川河口域潮間帯に設置しました。
(国土交通省庄内川河川事務所の了解を得ています)
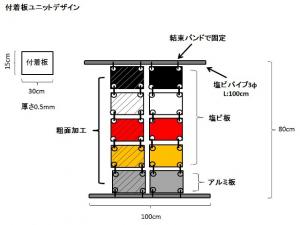
【実験板デザイン】
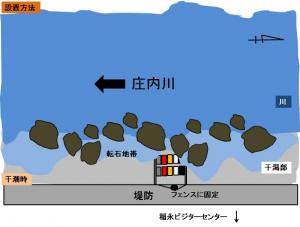
【設置場所(庄内川河口)】
~結果~
付着板を庄内川河口堤防に約7ヶ月間設置した結果、
大小様々なフジツボ類が付着しました(表-1)。
塩ビ板の色彩および表面条件の違いによる付着生物の
付着板への付きやすさは、付着個体数が1~4個体と少なく、
今回の実験では判断できませんでした。しかし、実験板の
材質による違いは顕著に見られ、フジツボ類は塩ビ板に比べて
アルミ(金属)板に付着しやすいことが分かりました。

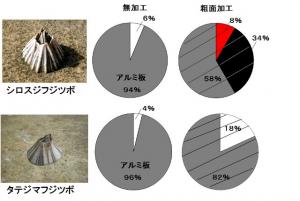
【付着したフジツボ類の割合(グラフ色は板色を表す)】
アルミ板では、粗面加工板に比べて無加工板の方が
フジツボ類は多く付着する結果となりました。当初は
板の表面に凹凸がある方が引っかかりやすく、
多くの生物が付くであろうと予想していたので、
想定外の結果となり驚きました。また、無加工板には
フジツボ類の他に小型カキ類が1個体確認されました。
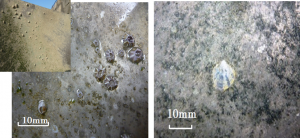
【アルミ板(無加工)に付着したフジツボ類(写真左)とカキ類(写真右)】
フジツボ類の付着がアルミ板で初めて確認されたのは
10月頃であり、その後徐々に分布の拡大と成長が見られました。
フジツボ類は殻長約1.2mmの小型個体から最大約13mmの大型
個体まで確認されました。
付着生物の着生には、それぞれの種に適した水温、水流、水深、
光環境条件が存在することが知られています。長期的な実験を行えば、
さらに多くの生物が付着し、くっつきやすい基盤が明らかとなる
のではないでしょうか。
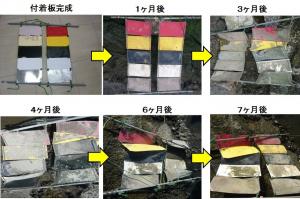
【付着板の時系列変化】
~まとめ~
実験から以下のことが明らかとなりました。
1)付着板にはシロスジフジツボとタテジマフジツボ、カキ類の3種の着生が確認された。
2)フジツボ類は塩ビ製板より、アルミ(金属)板に付着しやすい。
3)アルミ板では、付着板の表面状態に関わらず付着生物は着生する。
今回の実験で使用した付着板は、3月上旬頃から稲永ビジターセンター
1Fのフジツボコーナーに展示予定ですので、是非詳しい結果を
見に来て下さい。
カキの仲間がたくさんくっついている様子を観察する
ことができます。これらは「付着生物」と呼ばれており、
海水の影響がある水域で何かにくっついて生活する生き物です。
稲永ビジターセンター1Fのレクチャー室前には、
「フジツボコーナー」があり、フジツボの面白い生態を
紹介しています。フジツボを含めた付着生物がどんな物に
くっついて成長していくのか、分かりやすく展示できないかと考え、
色や材質の異なった板を河口域に設置して、生物が付着する様子を
観察してみました。
~方法~
実験に用いた板は4色(白・黒・赤・黄)の塩ビ板とアルミ板です。
また、実験板は表面状態の違いで、付着生物の付きやすさに差が見ら
れるのか調べるため、無加工の光沢板と表面に粗面加工を施した板の
2種類の実験板を作成しました。
実験は昨年5~12月の期間で実施し、実験板ユニットは稲永ビジター
センター前の庄内川河口域潮間帯に設置しました。
(国土交通省庄内川河川事務所の了解を得ています)
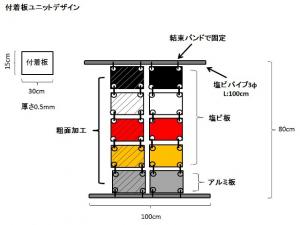
【実験板デザイン】
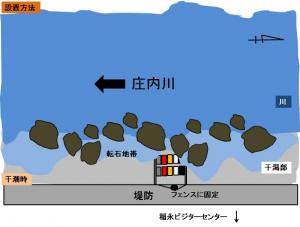
【設置場所(庄内川河口)】
~結果~
付着板を庄内川河口堤防に約7ヶ月間設置した結果、
大小様々なフジツボ類が付着しました(表-1)。
塩ビ板の色彩および表面条件の違いによる付着生物の
付着板への付きやすさは、付着個体数が1~4個体と少なく、
今回の実験では判断できませんでした。しかし、実験板の
材質による違いは顕著に見られ、フジツボ類は塩ビ板に比べて
アルミ(金属)板に付着しやすいことが分かりました。

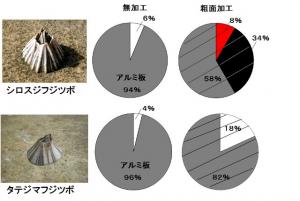
【付着したフジツボ類の割合(グラフ色は板色を表す)】
アルミ板では、粗面加工板に比べて無加工板の方が
フジツボ類は多く付着する結果となりました。当初は
板の表面に凹凸がある方が引っかかりやすく、
多くの生物が付くであろうと予想していたので、
想定外の結果となり驚きました。また、無加工板には
フジツボ類の他に小型カキ類が1個体確認されました。
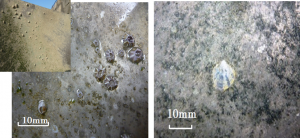
【アルミ板(無加工)に付着したフジツボ類(写真左)とカキ類(写真右)】
フジツボ類の付着がアルミ板で初めて確認されたのは
10月頃であり、その後徐々に分布の拡大と成長が見られました。
フジツボ類は殻長約1.2mmの小型個体から最大約13mmの大型
個体まで確認されました。
付着生物の着生には、それぞれの種に適した水温、水流、水深、
光環境条件が存在することが知られています。長期的な実験を行えば、
さらに多くの生物が付着し、くっつきやすい基盤が明らかとなる
のではないでしょうか。
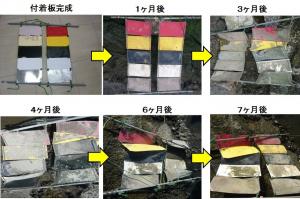
【付着板の時系列変化】
~まとめ~
実験から以下のことが明らかとなりました。
1)付着板にはシロスジフジツボとタテジマフジツボ、カキ類の3種の着生が確認された。
2)フジツボ類は塩ビ製板より、アルミ(金属)板に付着しやすい。
3)アルミ板では、付着板の表面状態に関わらず付着生物は着生する。
今回の実験で使用した付着板は、3月上旬頃から稲永ビジターセンター
1Fのフジツボコーナーに展示予定ですので、是非詳しい結果を
見に来て下さい。