立山
【シンポジウム】 未来につなぐ北アルプス。登山道について学び考える1日目
2025年01月31日
立山
こんにちは!立山管理官事務所の一ノ枝です。
令和7年2月15,16日に「北アルプストレイルプログラムあり方検討会 シンポジウム(in富山) 持続可能な登山道維持について考える」を開催します。
今回は1日目の内容に関して注目の登壇者やテーマ内容をピックアップしています!山を愛し、その地を守るために情熱を注ぐ方々が、貴重な知見を共有してくださいます。北アルプス好きなら絶対に聞き逃せない内容です!
<こんな方にはぜひオススメです!>
事前申込み制(入場無料)となっております。
詳細・お申込みは以下リンクから↓
https://nationalpark-japanesealpstrail.jp/toyama-news/447/
では早速1日目の登壇者の方をご紹介します。
令和7年2月15,16日に「北アルプストレイルプログラムあり方検討会 シンポジウム(in富山) 持続可能な登山道維持について考える」を開催します。
今回は1日目の内容に関して注目の登壇者やテーマ内容をピックアップしています!山を愛し、その地を守るために情熱を注ぐ方々が、貴重な知見を共有してくださいます。北アルプス好きなら絶対に聞き逃せない内容です!
<こんな方にはぜひオススメです!>
- 北アルプスで登山を楽しんでいる!
- 山岳環境保全や自然保護に関心がある!
- 登山道整備や地域活性化に興味がある!
事前申込み制(入場無料)となっております。
詳細・お申込みは以下リンクから↓
https://nationalpark-japanesealpstrail.jp/toyama-news/447/
では早速1日目の登壇者の方をご紹介します。
佐々木 泉氏(阿曽原温泉小屋) 1日目登壇

テーマ:黒部山域における登山道維持の取り組み
「黒部峡谷」その深いV字谷は、景色として美しいだけではなく険しい環境でもあります。阿曽原温泉小屋を営む佐々木さんは、このエリアの登山道を維持するため日々尽力されています。
「黒部に怪我なし」
黒部に伝わることわざです。 この道でつまずいたり転んだりした場合は怪我では済まないぞという意味で使われています。そんな場所で日々暮らして登山者を守り続けている佐々木氏にご登壇いただきます。

<注目ポイント>
- 遭難防止と登山道の重要性
黒部峡谷では、自然の厳しさから事故や遭難救助が多発するエリアもあります。佐々木氏は、遭難救助に繋がりにくい道の設定や、安全に登山するための登山道維持に関して取組み事例を紹介頂きます。 - 低い標高エリアの課題
北アルプスの中では標高が低い方であり、登山道では草刈りや自然災害等に伴う道の補修が必要になる頻度も高く、日々の維持には大きな負担となります。この問題を解決するための人材の確保について考えます。
続いてご登壇いただくのがこの方です!
伊藤 二朗 氏(雲ノ平山荘) 1日目登壇

テーマ:雲ノ平周辺の持続的な登山道維持と植生復元の取り組み
「最後の秘境」とも称される北アルプスの最奥部に位置する雲ノ平。その溶岩台地からなる美しい高山帯で、登山道周辺の荒廃が生じており、植生の復元や持続的な登山道の管理に対する課題に向き合われています。日本の国立公園のあるべき姿を提唱している伊藤氏にご登壇いただきます!

<注目ポイント>
- 登山道整備と環境保護のバランス
特別保護地区での登山道の公共工事整備に対する課題意識など国立公園でも特に原生的な自然が残るエリアの利用と保護に関して現場での取組や問題点を発表頂きます。 - 長期的視点で考える自然環境の復元
高山帯で荒廃した植生を元に戻すのは、数年単位では解決できません。大学と連携した調査から始まり、雲ノ平トレイルクラブの立ち上げなど、ハイカーが自然環境の保護に参画する仕組み作りも進めており、より持続的な管理体制の構築に向けた取組内容について学びます。 - 秘境ならではの課題
アクセスが困難な地域では、整備人材の確保や資材運搬にも一苦労。現場のリアルな課題についても共有頂きます。
次にこの方にご登壇いただきます。
大宮 徹氏(NPO法人富山県自然保護協会) 1日目登壇
テーマ:奥黒部登山道状況調査と折立地区における土壌浸食箇所の試験対策
奥黒部・薬師岳へ入る玄関口「折立登山口」をご存じでしょうか?
このエリアの登山道では主に土壌浸食による荒廃が進む中、大宮氏は土壌浸食の調査と復元へ向けた対策に取り組まれています。

< 注目ポイント>
- 小さな影響が積み重なる登山道の荒廃
- GISを活用したデータ可視化
現状把握から得た情報を地図上で可視化し、対策を検討する際の意思決定や経年変化の把握に活用する技術としてGISを中心とした管理技術についてご紹介頂きます。登山道管理の効率性向上や見える化に活用できる内容に注目です。
お昼休憩の後、残りお2人の方にご登壇いただきます。
石川 吉典 氏(三俣山荘) 1日目登壇
テーマ:三俣における道直しボランティア整備の取り組み
奥黒部の広大なエリアには、管理者不在の登山道が点在します。小屋周辺の三俣蓮華岳や鷲羽岳周辺の地道も荒廃が進んでいましたが、小屋を主体とした補修を中心に行っています。近年、三俣山荘を拠点に「風景と道直し」が取組まれており、国立公園における優れた自然風景の保全と利用者による登山道を中心とした自然環境への影響について登山者が学ぶ機会を提供されています。

< 注目ポイント>
- 日常的な登山道維持の現場から
- 価値観を共有する道直しプログラム
- 次世代を育てる一歩
最後にご登壇いただくのがこの方です。
佐伯 高男 氏(立山ガイド協会) 1日目登壇
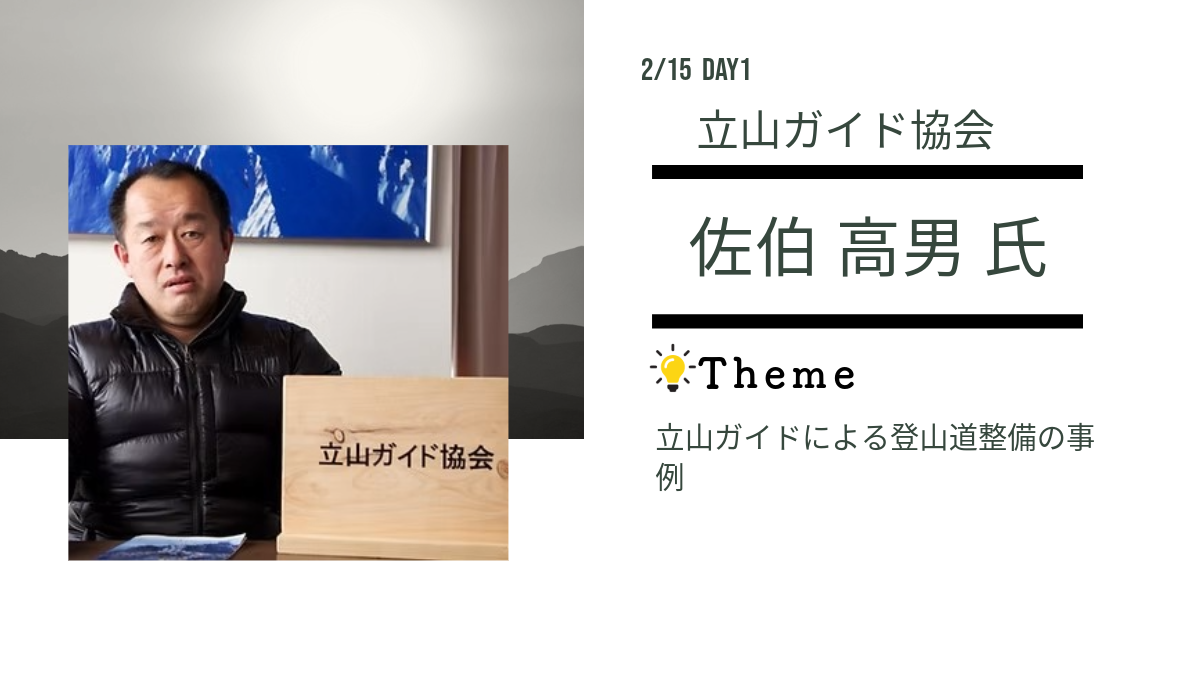 テーマ:立山ガイドによる登山道整備の事例
テーマ:立山ガイドによる登山道整備の事例
立山・剱岳の山域で活躍するガイドたちが、登山道維持にどのように関わっているかを
ご存じですか?立山ガイド協会の佐伯高男氏が、立山周辺での登山道整備について事例紹介を行います!特に富山県では学校登山(林間学校)でも使用する立山登山でも通る「一ノ越~雄山区間」での整備の実例を中心に、ガイドだからこそできる独自のアプローチをご共有いただきます。登山者が安全に歩ける道を守るだけでなく、その背景にある技術や人材育成についてもお話しいただきます!

< 注目ポイント >
・地域特性に合わせた登山道整備
立山剱エリアの利用者特有のニーズに応じた整備基準を設定しています。登山道の安全や質、持続可能な整備の方法について紹介いただきます。
・ シェルパ族との協力による石工技術の活用
ヒマラヤで活躍するシェルパ族の技術と知見を活かした石工技術を立山の整備にも活用しています。
・ガイドならでの整備との親和性
日々自然と利用者に接するガイドたちが直接関わることで、利用実態を把握しつつ行う整備の効果を解説いただきます。
持続可能な登山道維持とは?:有識者を含めたパネルディスカッション
1日目の後半パートはご登壇いただいた方々や有識者を含めたパネルディスカッションを行います!こちらはオンライン配信はなく会場のみとなります。
それぞれの立場や経験からみた持続可能な登山道の維持管理とは?どういった計画、管理であれば機能し、未来に続く登山道につなげることができるのか?
ディスカッションいただきます!

【登壇者(パネルディスカッション)】
野川 裕史氏(環境省中部山岳国立公園管理事務所長)
中森 健太氏(環境省立山管理官)
上田 英久氏(富山県自然保護課長)
佐々木 泉氏(朝日黒部山域 阿曽原温泉小屋)
大宮 徹氏(NPO法人 富山県自然保護協会)
伊藤 敦子氏(薬師岳奥黒部山域 三俣山荘)
佐伯 高男氏(立山剱山域 立山ガイド協会)
下嶋 聖氏(東京農業大学)
勝俣 隆氏(一般社団法人 トレイルブレイズハイキング研究所)
大土 洋史氏(株式会社YAMAP)
開澤 義浩氏(富山県山岳連盟)
申し込み(入場無料)*事前申込み制(オンライン視聴あり)
本シンポジウムは、北アルプスの「いま」と「未来」を知る絶好の機会です。未来の北アルプスを守る一歩を、一緒に考えてみませんか?
事前申込み制(入場無料)となっております。
詳細・お申込みは以下リンクから↓
https://nationalpark-japanesealpstrail.jp/toyama-news/447/
皆さまのご参加を心よりお待ちしております!!

