2013年2月19日
2件の記事があります。
2013年02月19日稲永ヨシ原の1年
国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子
稲永ビジターセンターから庄内川沿いに北(上流)へ向かって5分程度歩いた場所に、
ヨシという植物が群生する小さな干潟があります。
私たちはここを「稲永(いなえ)ヨシ原」と呼んでいます。
.jpg)
【稲永ヨシ原。コンクリートのスロープがあるのが特徴です。】
稲永ヨシ原は、国指定藤前干潟鳥獣保護区全体から見ると、
とても小さな面積の場所なのですが、
人と生き物の接点として非常に大事な場所となっています。
ここには、ヨシ原、砂干潟、泥干潟、転石、コンクリートの割れ目という多様な環境が
小規模ながらも集まっており、一度に多様な生き物を見ることができます。
生き物を探し、生き物によってすむ場所が違うことを見て学ぶことのできる
干潟の生き物の観察にはうってつけの場所です。

【子どもたちに大人気のカニもたくさんの種類が見られます。】
また、ここは、冬に訪れる多くのカモやカモメが休み、餌を採る場所となっています。
そして、これを見るためにカメラマンやバードウォッチングをする人が
たくさん訪れます。
.jpg)
【スロープで休むカモとカモメたち】
稲永ビジターセンターや市民団体などが、
稲永ヨシ原の生き物観察会や野鳥観察会、ヨシ刈りなどの
イベントを頻繁に行っている場所でもあります。
また、大学や市民団体によって生き物などの調査も行われています。
.jpg)
【稲永ヨシ原の生き物観察会】
さらに、ここは、堤防の形状から庄内川の水の流れがぶつかる場所となっているため
プラスチック製品などのごみが大量に漂着し、とどまる場所となってしまっています。
地元の方などによる清掃が行われ、維持されている場所でもあるのです。
.jpg)
【地元の方の清掃活動】
この約1年間、私たちはこの稲永ヨシ原の様子を記録してきました。
春に芽を出し、2mほどの長さまで成長した後、
穂を出して枯れるヨシとヨシ原の変化を追うことができました。

【稲永ヨシ原の1年】
今現在、ヨシは枯れており、稲永ヨシ原に棲むカニなどの生き物も影を潜めています。
一見とても寂しい景色が広がっていますが、
先週、泥の中から、小さなヨシの新しい芽が出ているのをみつけました。
3月も終わりになれば、ピンと上に伸びた若々しい緑色をした茎と葉が見られるはずです。

【長さ5cmほどのヨシの芽】
もうすぐ、稲永ヨシ原の生き物たちが活発に活動する季節がまた巡ってきます。
今年も子ども達が生き物をみつけ、喜ぶ声がたくさん聞けたら良いです。
今後もこの稲永ヨシ原を見ていきたいと思います。
~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~
つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。
みんなで作る人と生きものの絆。
ヨシという植物が群生する小さな干潟があります。
私たちはここを「稲永(いなえ)ヨシ原」と呼んでいます。
.jpg)
【稲永ヨシ原。コンクリートのスロープがあるのが特徴です。】
稲永ヨシ原は、国指定藤前干潟鳥獣保護区全体から見ると、
とても小さな面積の場所なのですが、
人と生き物の接点として非常に大事な場所となっています。
ここには、ヨシ原、砂干潟、泥干潟、転石、コンクリートの割れ目という多様な環境が
小規模ながらも集まっており、一度に多様な生き物を見ることができます。
生き物を探し、生き物によってすむ場所が違うことを見て学ぶことのできる
干潟の生き物の観察にはうってつけの場所です。

【子どもたちに大人気のカニもたくさんの種類が見られます。】
また、ここは、冬に訪れる多くのカモやカモメが休み、餌を採る場所となっています。
そして、これを見るためにカメラマンやバードウォッチングをする人が
たくさん訪れます。
.jpg)
【スロープで休むカモとカモメたち】
稲永ビジターセンターや市民団体などが、
稲永ヨシ原の生き物観察会や野鳥観察会、ヨシ刈りなどの
イベントを頻繁に行っている場所でもあります。
また、大学や市民団体によって生き物などの調査も行われています。
.jpg)
【稲永ヨシ原の生き物観察会】
さらに、ここは、堤防の形状から庄内川の水の流れがぶつかる場所となっているため
プラスチック製品などのごみが大量に漂着し、とどまる場所となってしまっています。
地元の方などによる清掃が行われ、維持されている場所でもあるのです。
.jpg)
【地元の方の清掃活動】
この約1年間、私たちはこの稲永ヨシ原の様子を記録してきました。
春に芽を出し、2mほどの長さまで成長した後、
穂を出して枯れるヨシとヨシ原の変化を追うことができました。

【稲永ヨシ原の1年】
今現在、ヨシは枯れており、稲永ヨシ原に棲むカニなどの生き物も影を潜めています。
一見とても寂しい景色が広がっていますが、
先週、泥の中から、小さなヨシの新しい芽が出ているのをみつけました。
3月も終わりになれば、ピンと上に伸びた若々しい緑色をした茎と葉が見られるはずです。

【長さ5cmほどのヨシの芽】
もうすぐ、稲永ヨシ原の生き物たちが活発に活動する季節がまた巡ってきます。
今年も子ども達が生き物をみつけ、喜ぶ声がたくさん聞けたら良いです。
今後もこの稲永ヨシ原を見ていきたいと思います。
~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~
つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。
みんなで作る人と生きものの絆。

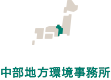
「閉まっている間は何をしているのだろう?」と、着任前は不思議に思っていたのですが…。
閉まってはいても、上高地は動いていました。
端的に言うと、来年度の準備ですが、内容は盛りだくさんです。
利用者がいない閉山期にしか出来ない施設の補修、危険木の伐採等の工事で、現場は天候(雪)と向き合いながら作業を進めています。
また、マイカー規制のような上高地の利用に関する多くの『ルール』についての会議や打合せ、配布資料(ポスター)作成などなど。こうやってシーズンを迎えるのかと、感心しきりです。
私はといえば、開山期のまとめの事務作業がメインですが、パークボランティアの定例会にて来年度の活動計画を練ったり、勉強会のお手伝いをしています。
パークボランティアの定例会・勉強会 の様子
先週は、乗鞍高原休暇村にて開催中のAR写真展(2月13日~3月15日・8:00~18:00)の設置のお手伝いもしてきました。
おや? 冬場は現場には出ないのかな?」とお思いでしょうか?
いえいえ、閉山期の利用者の状況調査や施設点検があります。
先々週末に、2回目の冬期調査に行ってきました。
この日はあいにくの雪(前日は快晴)でしたが、釜トンネルから上高地を目指す沢山の方へ、入山届の提出(ご存じない方もおられました)をはじめとした『冬期利用ルール』の周知を行いました。
釜トンネルにて入山者への『冬期利用ルール』周知状況
冬の上高地は冬山登山と同様の装備・知識が必要になります。また、入山者の増加やルール・マナー違反によって自然環境への影響が心配されています。このため、冬期入山者の安全確保と自然環境保全を目的として、関係機関で『冬期利用ルール』を策定して利用者に遵守を呼びかけています。
『上高地冬期利用ルール』
●必ず入山届を提出してください。
●雪崩・落石、地吹雪等に十分注意してください。
●湿原等には踏み込まないでください。
●用便は冬期トイレを使用してください。
●テントはキャンプ指定地(小梨平)で張ってください。
●ゴミや食料は必ずお持ち帰りください。
http://c-chubu.env.go.jp/nagano/pre_2012/1226a.html
約2時間、入山される方にお声がけしたのち、上高地へ向けて出発。
この日も、雪上に食品の包装紙等のゴミやトイレ跡が多く残されていました。
また、道中で、4箇所ある冬期トイレ(大正池・中の瀬・バスターミナル・小梨)の状況確認も行いました。
バスターミナルのトイレは屋根からの落雪のため、案内表示が見づらくなっていたため、除雪をしました。
ターミナルトイレの除雪作業、冬期トイレは建物裏にあります。
当日は、13時の時点で-8℃と冷え込みはさほど厳しくなかったですが、風が吹いたため、時折吹雪となり、自然の厳しさを体感しました。