2012年8月21日
3件の記事があります。
2012年08月21日あるべき姿をお守りします!
上信越高原国立公園 万座 アクティブレンジャー 小林映絵
先日、草津町にて“とある任務”を総勢33名と行いました!その“とある任務”とは!?
“外来生物(オオハンゴンソウ)の防除作業”です。昨年に引き続き「西の河原園地」で、多くの関係者にご協力頂き作業を行いました。大きな株は昨年に比べ減少していたのですが、やはりその生命力は強いですね。昨年度防除作業を行った際、根からの引き抜き作業が間に合わなかったところは刈り取りを行いました。その刈り取りを行った場所からは、小さな株が「わさっ」という感じで出ていました。花芽が付いていない事が救いでしたが、オオハンゴンソウさん、生命力強すぎです。

【オオハンゴンソウ】

【防除作業中です!】
今回の防除対象オオハンゴンソウについてこの場で、簡単に説明を。。。
オオハンゴンソウの原産国は北アメリカで、明治中期に観賞用として日本に持ち込まれました。その後、野生化し繁殖力が強く、在来種を駆逐してしまう事から特定外来生物に指定され、【外来生物法】が適用される植物となっています。
この「西の河原園地」でもものすごいスピードで繁茂し、本来そこにあるべき植物の住み処が奪われてしまっています。やはり、その土地ならではの景色を見たいですよね。
前回は、大きな株を中心に防除を行いましたが、今回は、2m程の株から、未だ花芽を付けていない手のひらサイズの株も対象に地道に抜き取り作業を行いました。いずれも根が張っていてなかなか抜けない、抜けない。「ふんぬ~!!」っと渾身の力を振り絞り、頑張りました!

【最後にみんなで記念撮影】
2時間という限られた時間ではありましたが、種を付ける前に作業が行えたのでオオハンゴンソウの広がりを抑えられたと感じています。ただし、1・2年ではそう簡単に根絶はできないのでこれからも協力を頂きながら防除作業を行っていきたいと思います。
※なお、特定外来生物は、栽培・運搬・販売など取扱いには規制が係って、防除を行う際にも十分な注意が必要となってきます。見つけた場合は、環境省へご相談・ご連絡頂けると有り難いです。
“外来生物(オオハンゴンソウ)の防除作業”です。昨年に引き続き「西の河原園地」で、多くの関係者にご協力頂き作業を行いました。大きな株は昨年に比べ減少していたのですが、やはりその生命力は強いですね。昨年度防除作業を行った際、根からの引き抜き作業が間に合わなかったところは刈り取りを行いました。その刈り取りを行った場所からは、小さな株が「わさっ」という感じで出ていました。花芽が付いていない事が救いでしたが、オオハンゴンソウさん、生命力強すぎです。

【オオハンゴンソウ】

【防除作業中です!】
今回の防除対象オオハンゴンソウについてこの場で、簡単に説明を。。。
オオハンゴンソウの原産国は北アメリカで、明治中期に観賞用として日本に持ち込まれました。その後、野生化し繁殖力が強く、在来種を駆逐してしまう事から特定外来生物に指定され、【外来生物法】が適用される植物となっています。
この「西の河原園地」でもものすごいスピードで繁茂し、本来そこにあるべき植物の住み処が奪われてしまっています。やはり、その土地ならではの景色を見たいですよね。
前回は、大きな株を中心に防除を行いましたが、今回は、2m程の株から、未だ花芽を付けていない手のひらサイズの株も対象に地道に抜き取り作業を行いました。いずれも根が張っていてなかなか抜けない、抜けない。「ふんぬ~!!」っと渾身の力を振り絞り、頑張りました!

【最後にみんなで記念撮影】
2時間という限られた時間ではありましたが、種を付ける前に作業が行えたのでオオハンゴンソウの広がりを抑えられたと感じています。ただし、1・2年ではそう簡単に根絶はできないのでこれからも協力を頂きながら防除作業を行っていきたいと思います。
※なお、特定外来生物は、栽培・運搬・販売など取扱いには規制が係って、防除を行う際にも十分な注意が必要となってきます。見つけた場合は、環境省へご相談・ご連絡頂けると有り難いです。
2012年08月21日外来植物除去作業 白山・赤兎山
白山国立公園 白山 アクティブレンジャー 世良裕次
こんにちは。
白峰は昨日に続き本日も快晴です。
先週末は3日連続で山を登ったり下りたりしていましたが、天候には恵まれず、18日に至っては急な土砂降りにレインウェアを着る間もなくずぶ濡れとなり、更にはヒョウにも降られました。
落雷も多く、自然の厳しさにただただ登山道を歩くだけのちっぽけな私の姿があり、人間の小ささを感じました。
さて、山上へは人間の小ささを感じに行っていただけではありません。
18日は、外来植物除去のボランティア登録している人たちで甚之助避難小屋~南竜山荘(石川県白山市)までの間の道で、19日には一般参加の方も交え、赤兎山(福井県勝山市)で白山における外来植物であるオオバコの除去作業を行ってきました。

【作業中@赤兎山】
外来生物というのは決して外国から来たものだけを指すのではなく、もともとその地に無いものが人間の力によって運ばれたものも指します。
皆さんの家の側にもオオバコが沢山あるように、オオバコは低地性(麓)の植物なのです。
山上に絨毯のごとく咲き並ぶキレイなオオバコの畑の中で、黙々と作業を続けていると、どうしても「このやろー」と力が入ってしまいます。
オオバコはただ自然の摂理に従って、子孫を残しているだけなので、本来ごめんね!と気持ちを込めて抜いてあげるべきだと思うのですが・・。
ではオオバコは何故山上へと分布を拡げているのでしょうか?
勝手に登山して行く?
オオバコの種が空を舞う?
実は私達の靴の裏などに付着し、一緒に登山をしています。
また、山上で避難小屋などを建てる資材などに付着して登って行くケースも見られます。
山上にはハクサンオオバコという高山植物があり、交雑してしまっている例も確認されています。
人間が知らず知らずのうちに持ち込んだ外来植物によって、白山の生態系を崩してしまう恐れがあります。
数百年、数千年、数万年と培ってきた神秘的な白山の生態系や景観を、たかだか数十年でその生態系や美しい景色などを崩してしまう、自然に対して影響力の大きな大きな人間の姿があるのです。

【手前に2本ビョーンと伸びているのがオオバコの花です。奧から大きな人間の姿が!!】
「地球はいずれ温暖化していくのだから・・」と地球温暖化を傍観する意見があるように、「外から入ってくる生きものはいずれ入って来るだろう」「人間という手段を使って分布を拡げている」などの意見もあるかもしれません。
個人的にはその考えは間違いとは思いません。
ただ、人間の活動が加わることによって生態系の破壊や温暖化もそうですが、そのスピードは何倍何百倍にもなってしまいます。
実際に今回の活動を通して、果てしないこの作業にうんざりしている方もいるかもしれません。
ただ、山上にこれだけの外来植物が繁茂している現状を体で実感し、私達人間が自然と共生していく中で、人間が自然に対してどのような態度を取っていくべきなのか?等、自然に対しての思いやりの気持ちについて少しでも考えてもらえたらと思います。

【美しい白山をいつまでも】
白峰は昨日に続き本日も快晴です。
先週末は3日連続で山を登ったり下りたりしていましたが、天候には恵まれず、18日に至っては急な土砂降りにレインウェアを着る間もなくずぶ濡れとなり、更にはヒョウにも降られました。
落雷も多く、自然の厳しさにただただ登山道を歩くだけのちっぽけな私の姿があり、人間の小ささを感じました。
さて、山上へは人間の小ささを感じに行っていただけではありません。
18日は、外来植物除去のボランティア登録している人たちで甚之助避難小屋~南竜山荘(石川県白山市)までの間の道で、19日には一般参加の方も交え、赤兎山(福井県勝山市)で白山における外来植物であるオオバコの除去作業を行ってきました。
【作業中@赤兎山】
外来生物というのは決して外国から来たものだけを指すのではなく、もともとその地に無いものが人間の力によって運ばれたものも指します。
皆さんの家の側にもオオバコが沢山あるように、オオバコは低地性(麓)の植物なのです。
山上に絨毯のごとく咲き並ぶキレイなオオバコの畑の中で、黙々と作業を続けていると、どうしても「このやろー」と力が入ってしまいます。
オオバコはただ自然の摂理に従って、子孫を残しているだけなので、本来ごめんね!と気持ちを込めて抜いてあげるべきだと思うのですが・・。
ではオオバコは何故山上へと分布を拡げているのでしょうか?
勝手に登山して行く?
オオバコの種が空を舞う?
実は私達の靴の裏などに付着し、一緒に登山をしています。
また、山上で避難小屋などを建てる資材などに付着して登って行くケースも見られます。
山上にはハクサンオオバコという高山植物があり、交雑してしまっている例も確認されています。
人間が知らず知らずのうちに持ち込んだ外来植物によって、白山の生態系を崩してしまう恐れがあります。
数百年、数千年、数万年と培ってきた神秘的な白山の生態系や景観を、たかだか数十年でその生態系や美しい景色などを崩してしまう、自然に対して影響力の大きな大きな人間の姿があるのです。
【手前に2本ビョーンと伸びているのがオオバコの花です。奧から大きな人間の姿が!!】
「地球はいずれ温暖化していくのだから・・」と地球温暖化を傍観する意見があるように、「外から入ってくる生きものはいずれ入って来るだろう」「人間という手段を使って分布を拡げている」などの意見もあるかもしれません。
個人的にはその考えは間違いとは思いません。
ただ、人間の活動が加わることによって生態系の破壊や温暖化もそうですが、そのスピードは何倍何百倍にもなってしまいます。
実際に今回の活動を通して、果てしないこの作業にうんざりしている方もいるかもしれません。
ただ、山上にこれだけの外来植物が繁茂している現状を体で実感し、私達人間が自然と共生していく中で、人間が自然に対してどのような態度を取っていくべきなのか?等、自然に対しての思いやりの気持ちについて少しでも考えてもらえたらと思います。
【美しい白山をいつまでも】

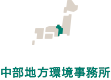
8月16日に藤前活動センターにて行われました!
非常に蒸し暑い日でしたが、夏休みでお盆休み期間中であったことから、
ご家族での参加がたくさんありました。
中には、福岡県から藤前干潟に来て、観察会に参加してくださった方もいました。
【藤前活動センターのレクチャー室に集まりました】
今回の観察会のテーマは、ズバリ「二枚貝」。
アサリのように2枚の貝殻が合わさってできている貝たちに注目してみました。
(※藤前干潟にはアサリはあまりいません。)
二枚貝のことを知る第一歩として、まずはハマグリの貝殻を用いて
「貝合わせ」という遊びにチャレンジしました。
【きれいなハマグリの貝殻。昔は藤前干潟でもハマグリが捕れたそうです】
「貝合わせ」は、平安時代から行われている神経衰弱のような遊びです。
(昔は、「貝覆い」と呼ばれていたようです。)
二枚貝の2枚の貝殻の外側を上にして別々に置き、その模様や形などを見て、
ペアの2枚をみつけます。
これは、一つ一つの貝の貝殻が形や大きさが異なり、
同じ貝の貝殻でないと絶対に組み合わさらないからできる遊びなんです。
一見、全部同じようにみえる貝にも個性=多様性があるんですよ。
【簡単なようで以外に難しい・・・?】
そして、いよいよ干潟へ出て、二枚貝を始めとする生き物探しへ。
【こんなに広大な干潟が出ていました】
みお筋と呼ばれる干潟の少し深いところにしかけた土管の中にいる生き物を探したり、
泥の中を掘ってみたり・・・。
【何がみつかったでしょうか?】
再び、室内に戻って、生き物を観察してみたところ、
ヤマトシジミ、オキシジミ、ソトオリガイなどの二枚貝の他に、
マハゼ、コチ、エビなどを探すことができました。
その中でもお味噌汁に入れて食べるヤマトシジミがとってもたくさんいることが分かりました。
そして、夏の風物詩、ウナギも一匹、土管の中からみつかりましたよ!
【みつかった二枚貝】
生き物の観察の後は干潟から持ち帰ってきた二枚貝であるヤマトシジミの貝殻の内側に
絵を描いて自分だけのオリジナル貝合わせを作成しました。
【一生懸命描いてくれました】
最後は、振り返りとして二枚貝の役割について学びました。
二枚貝は、水の中に溶け込んでいる有機物を餌としています。
二枚貝が有機物をたくさん餌として食べてくれると、
水の富栄養化が抑制され、赤潮、ひいては青潮という海の環境の悪化を防ぐことができます。
貝はあまり動かないし、中身は見えないし、一見地味な生き物ですが、その力は強大です!
二枚貝がたくさん生息する藤前干潟などの干潟をこれ以上減らしたくはありませんね。
このように、最後はちょっと難しい話もありましたが、皆さんには楽しく、
観察会を終えてもらえたようです。
また、藤前干潟に来て、生き物にふれあい、学んでほしいと思います。
~藤前干潟は2012年11月18日で、ラムサール条約登録10周年を迎えます~